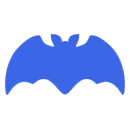|
あなたは18歳以上ですか?
サイトにはアダルトコンテンツが含まれています。 |
|
|
いいえ
はい、18歳以上です
|
|
|
あなたは18歳以上ですか?
サイトにはアダルトコンテンツが含まれています。 |
|
|
いいえ
はい、18歳以上です
|
|
大変申し訳ないのですが、あなたがアクセスしようとしたページは削除されたかURLが変更されています。